
基礎の基礎から応用編、さらにはレイマーチング・GLSLSound まで! GLSL スクール 2020 募集開始!
2020 年 11 月開講
本スクールは、GLSL を利用したシェーダコーディングを基礎からしっかり学ぶことができる シェーダ入門者向け のスクールです。
シェーダと一口に言っても、その種類やユースケース・プラットフォームは様々です。WebGL を使ったウェブサイトのデザインや開発にシェーダを用いるのと、ゲームなどのエンターテイメント性の強いプラットフォームでシェーダを用いるのとでは、突き詰めていけばいろいろな部分で違いが出てくるのは、ある意味では当然だと言えるでしょう。しかし一方で、どのようにシェーダを扱うにせよ、基本となる概念や技術は共通する部分が多く存在することも事実です。
本スクールでは、トライ・アンド・エラーの行いやすいシェーダの実行環境として、WebGL と JavaScript を活用しています。普段は JavaScript をあまり使ったことが無い、という方にも気軽にシェーダに触れてみてほしいという思いから、本スクール独自の GLSL 学習用環境を提供する形になっていますので、普段はウェブ開発に携わっていないという方にも安心してご参加いただけます。
※上記で記載のある独自の学習用環境とは、Electron を利用して実装したオープンソースの GLSL 開発用エディタです。無償で利用でき、Windows 用と Mac 用を用意しています。
以下、スクールの講義内容などについて記載していきますので、興味のある方はぜひ受講をご検討ください。
コロナウィルス対策について
コロナウィルス感染症を予防する観点から、今開催のスクールでは リアルタイムの動画配信による リモート受講 での開催となります。
リモート受講では、講義の様子を YouTube Live の限定共有を設定した状態で リアルタイムに配信 します。限定配信にアクセスするためのリンクは当日までに受講者全員に共有します。
リモート受講の場合であっても、例年と同様のカリキュラム・サンプル等を用いた講義になりますので、実際に会場に来てもらうか・そうでないかという以外に違いは一切ありません。(カリキュラムの内容やサンプルについては毎年見直しを行っているので、まったく同じということはありませんが新しくなった最新版を提供する形になります)
また副産物的ではあるのですが、一度配信を行うと、その配信動画がアーカイブとして残りますので、万が一当日受講することが難しかった場合なども講義の実際の様子をあとから受講者さんの都合の良いタイミングで確認・復習することができます。
GLSL スクールの本講義カリキュラム
今回のスクールも主催者である杉本 雅広(すぎもとまさひろ)が責任を持って基本となる「本講義」を担当します。

- 杉本 雅広(本講義を担当)
- @h_doxas | Twitter
- WebGL 開発支援サイト wgld.org 運営
- WebGL スクールや勉強会の主催
本講義では、あまり極端な変化球のような内容ばかりにならないように、むしろ基本を重視した構成で講義を進めていきます。何事もまずは基本が大切ですので、しっかりと基礎の部分を固めることができるように、シェーダが動作する仕組みの部分からじっくりと取り組んでいきます。
また、シェーダを記述していく上で必要となる、数学の基本なども講義内容に含まれています。三角関数やベクトル、行列など、数学に対してはちょっと苦手意識があるという方にもわかりやすいよう、工夫して資料を作成しています。
もちろん、これらの基礎知識があることによって「初めてトライすることが可能になる応用技術や高度なテクニック」というのも世の中にはたくさんあります。そういった応用ワザについても、本講義はもちろんのこと、後述するプラスワン講義などで体験できるようにしていますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。
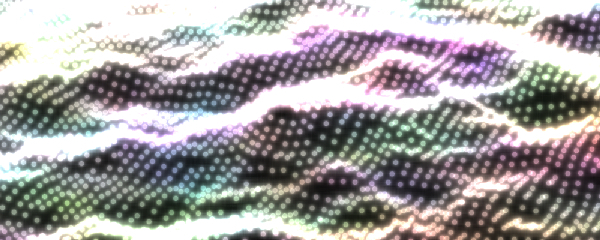
今回も豪華講師陣によるプラスワン講義を開催!
プラスワン講義は、ちょっとした課外授業のような肩肘張らない雰囲気で、広く様々な分野の方々から講義をしていただく特別授業です。こちらは本講義のあと、1 時間程度を目安に、シェーダや 3DCG 熟練者の講師の方から他ではちょっとお目にかかれないようなコアな講義を行ってもらうもの。
本講義では触れられることのないような応用技術、あるいはシェーダを活用した表現について、外部講師が独自のテーマで語ってくれます。
以下、簡単にですがプラスワン講義の講師のみなさんをご紹介します。
らくとあいすさん(@rakuraku_vtube)

シェーダを利用してサウンドを生成する…… そんな魔法のようなテクニックがこの世には存在します。
そして私の知る限り、らくとあいすさん以上の GLSLSound 奏者(奏者と言っていいのかどうかは正直わからないけど……)はいないと思います。単純に音楽の才能もそうなのでしょうが、ロジカルにシェーダを分析しながら音色を生み出していくその様子は本当に魔法のようです。
今回のプラスワン講義でも、GLSL を利用してサウンドを生成する GLSLSound をテーマに語っていただける予定です。
避雷さん(@lucknknock)

避雷さんは Unity 用の素材やシェーダを配布されたりもしているので、ご存知の方も多いかもしれません。
最近では、未踏プロジェクトに「シェーダライブコーディング・アーカイブシステムの作成」が採択され、ウェブ開発にも積極的に取り組んでいらっしゃいます。
今回のプラスワン講義では、そのあたりの話題も含めてシェーダをテーマにいろんなお話が聞けたらなと思っています。
ブタジエンさん(@butadiene121)
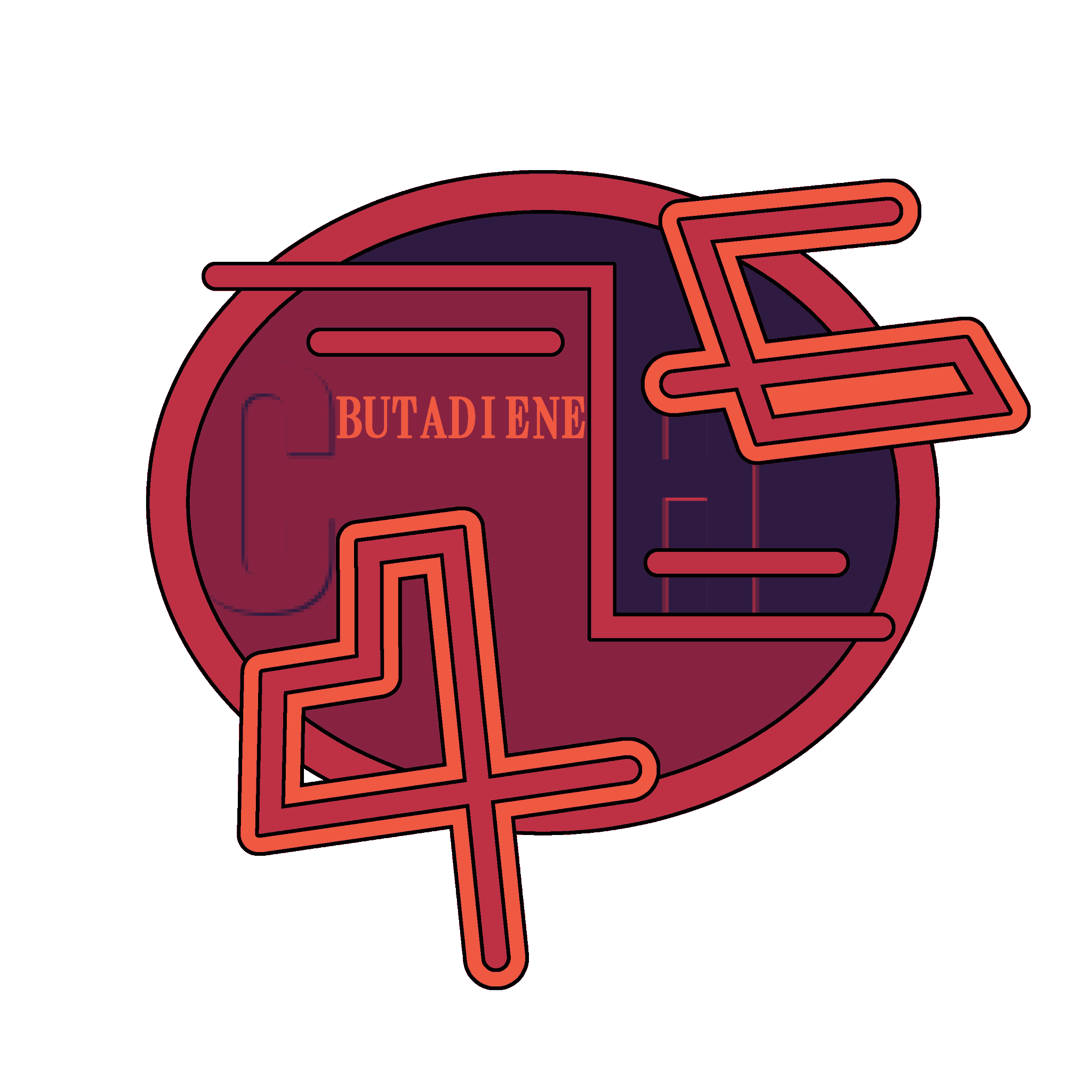
ブタジエンさんは、避雷さんと一緒に Shader1WeekCompo を主催するなど、プラットフォームを限定しない様々な分野で活動されています。
個人的に思い出深い話としては、実はブタジエンさんはちょっと前に一部の界隈で話題になった #つぶやきGLSL の考案者でもあるんですよね。
避雷さんにも同じことが言えると思うのですが、様々な新しいアイデアや新しい技術に挑戦している様子は見ていて本当に素晴らしいと思います。
今回のプラスワン講義では、レイマーチングのクオリティアップのテクニックなどを話してくださる予定です。
スクール全五回スケジュール
本スクールは、2020 年の 11 月 07 日(土曜日)に第一回が開催となります。
講義は原則隔週土曜日なので二週間ごとに講義が一回という感じになります。
なお、最終回となる第五回に関しては、講義を行うというよりも受講者みんなで作品を鑑賞したり、ライブコーディングを楽しんだりといったオマケ回的なイメージになっています。詳細については、以下をご覧ください。
| 日時 | 講義内容 | |
|---|---|---|
| 第一回 | 11月07日(土) | GLSL やシェーダの基礎知識を手に入れよう |
| 第二回 | 11月21日(土) | 頂点シェーダやテクスチャの使い方を知ろう |
| 第三回 | 12月05日(土) | フラグメントシェーダやフレームバッファを使いこなそう |
| 第四回 | 12月19日(土) | シェーダアートやクリエイティブコーディングに挑戦しよう |
| 第五回 | 01月16日(土) | みんなで作品発表・鑑賞会 ライブコーディング実演 etc... |
続いて簡単にですが、各回の概要を書いておきます。
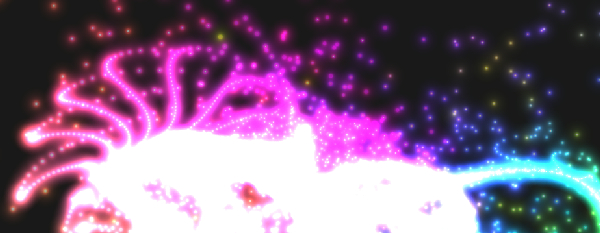
第一回
第一回は一般にシェーダと呼ばれている概念の説明や、シェーダと GLSL の関係、さらにはシェーダがどのようにグラフィックスを描くことに関係しているのかなど、基礎的な概念の部分からしっかりと講義を行います。
GLSL の基本的なお作法などもこの第一回でカバーしていきます。
例年の傾向として、この最初の講義はどうしても説明することが多くなるのでやや難しく感じてしまう場合が多いようです。とはいえ、やはり基本を押さえておくことは後々大きなアドバンテージになりますので、ぜひともがんばってもらいたいところです。
第二回
第二回は主となるテーマが「頂点シェーダ」となります。
頂点シェーダに特有な部分、頂点シェーダだからこそできる処理など、頂点シェーダの持つ特性を活かしたテクニックについて学びます。
とはいえ、ただ頂点シェーダだけを使うということではなく、もちろんフラグメントシェーダが出てくる場面もありますし、テクスチャなどの CG を構成する基本的な概念なども登場します。そういったことも踏まえると、どちらかというと基礎固め、という感じがニュアンスとしては近いかもしれません。
第三回
第三回は「フラグメントシェーダ」が主役です。
また、フラグメントシェーダを活用することで実現できるポストエフェクトなどのテクニックもここで登場します。
この第三回の講義が終わったあたりで、ほぼ基本的な部分は網羅した状態になります。これまでに解説・紹介したテクニックを組み合わせることで、人によっては簡単なデモ作品などを制作することもできるようになるはずです。
第四回
第四回は、これまでの講義内容を踏まえつつ、ひとつ上のレベルを目指す内容になります。
シェーダアートやクリエイティブコーディングのジャンルで見られるような、シェーダを活用しているからこそ実現可能なテクニックを重点的に扱っていきます。
第四回で登場するテクニックについては、その場でサッと理解するのは若干難しい高難易度な内容も含まれます。このあたりは、講義の時間内で理解してもらいたいというよりは、将来的にもしかしたら役に立つかもしれないし出し惜しみはせずに高難易度なものも紹介しよう、という気持ちで取り入れています。
第五回とプラスワン講義
プラスワン講義は、第三回および第四回の、本講義終了後に別枠として行います。
| 担当講師 | 講義内容 | |
|---|---|---|
| 第三回 | らくとあいすさん | サイン波からはじめる GLSLSound |
| 第四回 | 避雷さん | 最高のライブコーディング環境を作りたい |
| 第四回 | ブタジエンさん | レイマーチングを用いた ShaderArt 作成事例 |
| 第五回 | 講師のみんな | ライブコーディングやオマケ講義 |
本講義のあと、各々の回ごとに講師をバトンタッチしながら行う感じですね。
タイムスケジュールは原則、本講義のあと、プラスワン講義を行うスタイル。
適宜、休憩時間等を設けて進める形となります。
あくまでも目安ですが、時間は以下のような感じを想定しています。
| 本講義 | プラスワン講義 |
|---|---|
| 14:00 〜 16:50 | 17:00 〜 18:00 |
なお、第五回に関しては講義というよりは発表会のようなものを行う予定です。詳細は、スクールの運営中に受講者さんに都度連絡していきます。
発表会などを行ったあと、最後にエキシビジョンとしてライブコーディングをみんなで鑑賞できたらいいなと思っています。

受講料について
以下、受講料の一覧です。
全て 内税表記 ですので、下記料金以外に余分な消費税等をいただくことはありません。
| 支払い形態 | 受講料 | 備考 |
|---|---|---|
| 一般(一括) | 70,000 円 | 一括支払いで分割に比べて 15,000 円割引 |
| 一般(分割) | 85,000 円 | 分割回数や一回の支払額は相談して無理ない範囲で決めます |
| 学割(一括・分割) | 30,000 円 | ※学割の場合、一括・分割で受講料は変わりません |
※学割を希望される場合は、お手数ですが別途学生証などを拝見させていただきます。
受講料は原則として前払いでお願いしていますが、これは単にいたずらや事前連絡のない突然のキャンセル等を避けるためです。
たとえば一時的に収入が不安定な時期であるなど、なにかしらの事情がある場合はご相談いただければできるかぎり対応しますので、お気軽にご相談ください。個人運営のスクールなので、そのあたりは受講者さんの都合に合わせてできる限り調整します。
また、スクールの受講が確定するのは、申し込みいただいてから、折り返しこちらからご連絡を差し上げたあとになります。※これもいたずらなどの防止のためです。
お申し込みフォームから、必要事項をご入力いただき、お申し込みください。こちらから、遅くとも2~3日以内にはご連絡差し上げますのでそこで 確認が取れ次第スクールの受講が確定 となります。
特に、折り返しのご連絡を差し上げる都合上、メールアドレスの間違いにはご注意ください。また、3日以上経過してもこちらからのご連絡が届かない場合は、どこかでフィルタに掛かってしまったなど間違いが起こっている可能性もありますので、そういった場合は遠慮せず確認のご連絡をいただければと思います。
繰り返しになりますが フォームからの申し込み送信時点では受講が確定した状態ではありません ので、ご注意いただければと思います。
コロナウィルス対策について(再掲)
コロナウィルス感染症を予防する観点から、今開催のスクールでは リアルタイムの動画配信による リモート受講 での開催となります。
リモート受講では、講義の様子を YouTube Live の限定共有を設定した状態で リアルタイムに配信 します。限定配信にアクセスするためのリンクは当日までに受講者全員に共有します。
リモート受講の場合であっても、例年と同様のカリキュラム・サンプル等を用いた講義になりますので、実際に会場に来てもらうか・そうでないかという以外に違いは一切ありません。(カリキュラムの内容やサンプルについては毎年見直しを行っているので、まったく同じということはありませんが新しくなった最新版を提供する形になります)
また副産物的ではあるのですが、一度配信を行うと、その配信動画がアーカイブとして残りますので、万が一当日受講することが難しかった場合なども講義の実際の様子をあとから受講者さんの都合の良いタイミングで確認・復習することができます。
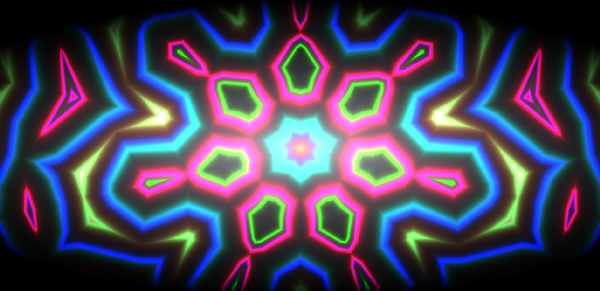
募集人数
今回のスクールでは、リモートでの開催になりますので会場の収容人数による制限などがなく、特に人数制限はありません。
ただ、当スクールは大きなチームで運営しているものではありませんので、想定以上に申し込み人数が多くなりすぎてしまうと個々の受講者さんたちを細かくサポートすることが難しくなってしまう可能性も考えられます。
そのような観点から、場合によっては人数制限を設けるかもしれません。(その場合は大変申し訳ありませんが先着順になります)
お支払い方法とお申し込み
受講料のお支払いは、銀行振込でお願いしています。クレジットカード等での決済はお受けできませんのでご了承ください。
企業や個人宛に、請求書の発行や領収証の発行等、必要に応じて対応できますのでお気軽にご相談ください。
お申し込みは、以下のフォームより、お願いします。
くれぐれも、入力間違いなどにご注意ください。
こちらから返信メールを送信させていただき、連絡が取れた方から受講が確定します。メールアドレスの記入にはご注意ください。
お問い合わせ
なにかご不明な点や、ご意見等がありましたら当サイトのお問合せページよりご連絡ください。できる限り迅速に返信させていただきます。



